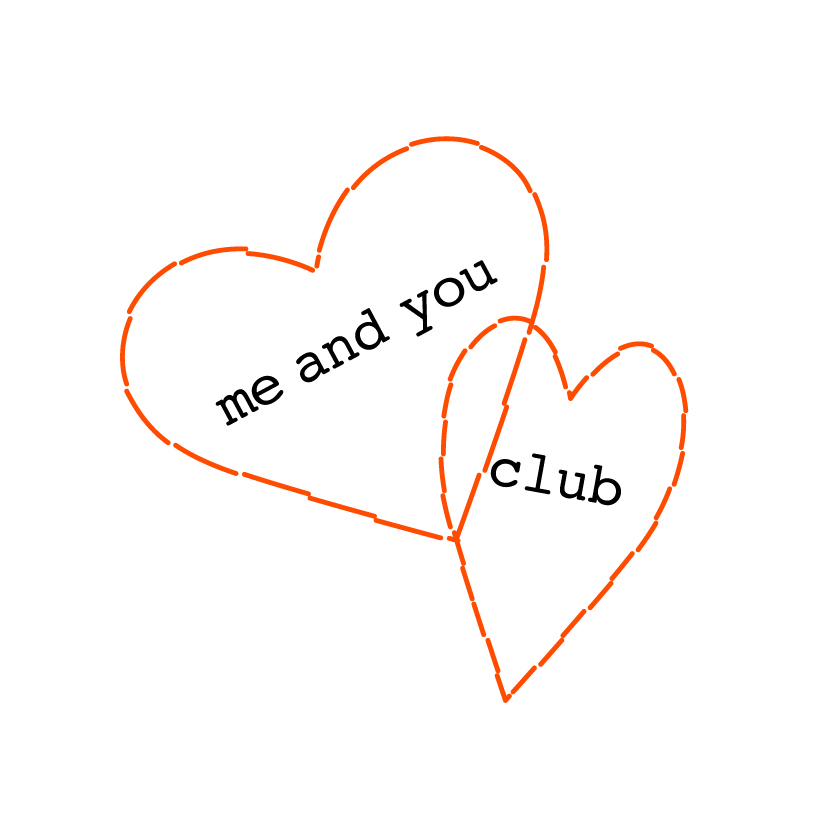先日、ユニバーサルシアター
「シネマ・チュプキ・タバタ」
に行きました。
映画のタイトルは、
「いのちのかたちー画家・絵本作家 いせひでこー」
トークショーがついていて、バリアフリーの音声ガイド制作の裏側もきけるということで、イヤホンで音声ガイドをききながら視聴することに。
ただ状況を説明するだけではなくて、台詞と台詞の間に邪魔にならないように、映像の雰囲気を壊すことなくそれに寄り添った言葉が与えられていると感じました。
音声ガイド制作には、めのみえない方からのきびしいフィードバックも反映されているとか。
たくさん説明するより、言葉になる前の言葉の余白を残しておくこと。
視覚的にみえないからといって、みえていないわけではなく、想像力を信頼する言葉選びをすること...
バリアフリー映画の制作には、そうでない映画よりも一層、異なるイメージが重なりをもつように想像力を深める作業があるのだと知りました。
(ただ、音声ガイドの国内普及率は、まだ2%ほど。そのうちの20%ほどを、シネマチュプキが担当しているという話も。)
今回は絵本や絵にまつわるドキュメンタリーだったために、絵にガイドをつけることに抵抗を感じた、という話から転じて、印象的な話がありました。
トークショーに参加されていた視覚障害者モニターの田中正子さんが、じぶんではみることのできない絵本をたくさん買って、プレゼントしたことー
あるとき、この映画館で映画と映画の休憩時間にゆっくりしていたら、絵本を読んでいる方がいて
その方が「よかったら読みましょうか?」と、読んできかせてくれたのだという。
「それでわたしは絵本に出会うことができたんです」
絵本に出会うことができたーその言葉が印象的でした。
トークショーでは音声ガイド制作者の遠藤郁美さんが、視覚障害者モニターの田中正子さんに、映画の中に登場する、「幼い子は微笑む」(絵:伊勢英子 詩:長田弘 講談社絵本)をよみきかせ。
お客さんも絵をことばで表現するという体験をして、みんなでイメージを共有しました。
私自身も、じぶんひとりではみることのできない絵本に出会うことができた、貴重な経験となりました。