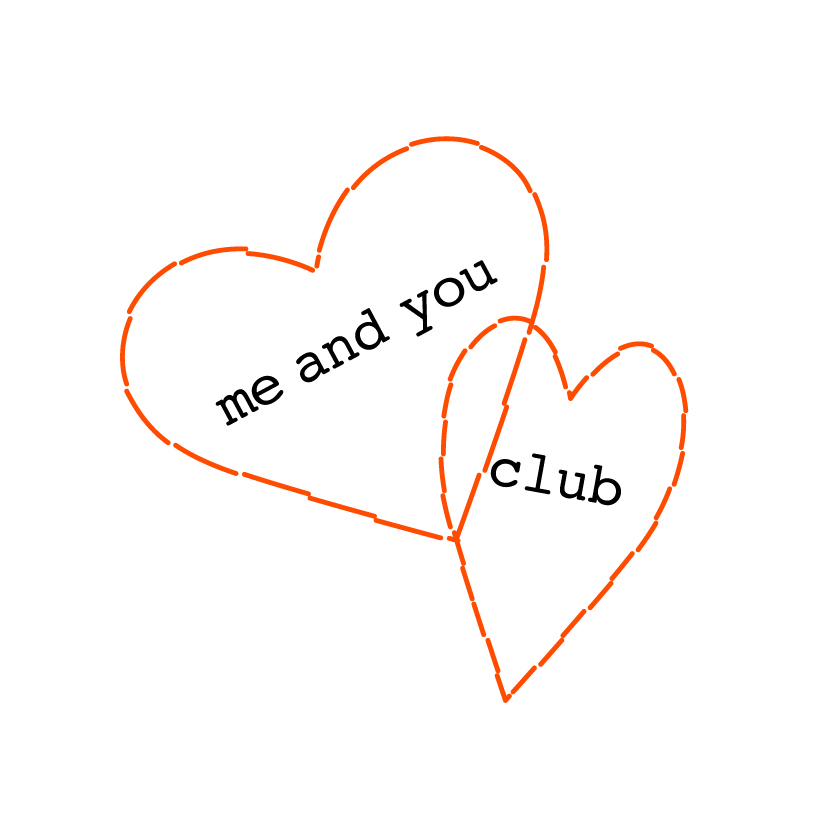母はいつも、猫を抱いたおばあちゃんの写真を大切に持っている。私は彼女を「猫のおばあちゃん」と呼んでいるが、本当の名前はツギノさんだということも知っている。ちなみに、猫の名前は太郎。母の両親は仕事でほとんど家にいなかったため、母は「私は猫のおばあちゃんに育てられたんだよ」といつも言う。
猫のおばあちゃんは明治生まれで、私が生まれる少し前に亡くなってしまったので写真でしか見たことがない。写真の中の彼女の印象は、朴訥とした木の工芸品と重なり、その上でまるくなっている太郎の背中が余計にやわらかく見える。彼女はとても勤勉で、女学校に行きたかったらしい。最初にお嫁に行った先での扱いがあまりに酷いのに耐えられなくて、夜に家を飛び出して、実家まで裸足で帰ってきたらしい。母はよくその話を私にしては、「あなたには猫のおばあちゃんの血が入っているね」と言う。私はそうかしらと思いながらも、なんとなく、朱色の着物を着ていて、手首が細くて、自分よりすこし若い女の子のことを思い浮かべる。きっと、深い山の峠を、足に傷をたくさん作りながら必死で越えたんだ。私は、その子のことを知っているような気がする。
ロシアのことをソビエト、フィリピンのことをフィーリピンと呼ぶツギノさんは、いくつもの戦争を知っている。戦争で息子を予科練に入れている。ツギノさんはまめに日記を書く人だったけど、戦争が終わったときに「残しとっちゃあいかん」と言って、全部焼き払ってしまった。私はその日記を読みたい。読めたらどんなにいいだろう。そしたらもっとツギノさんのことがわかるのに。ずっとずっと、もう無い日記のことを思っている。


2023/11/21 23:02